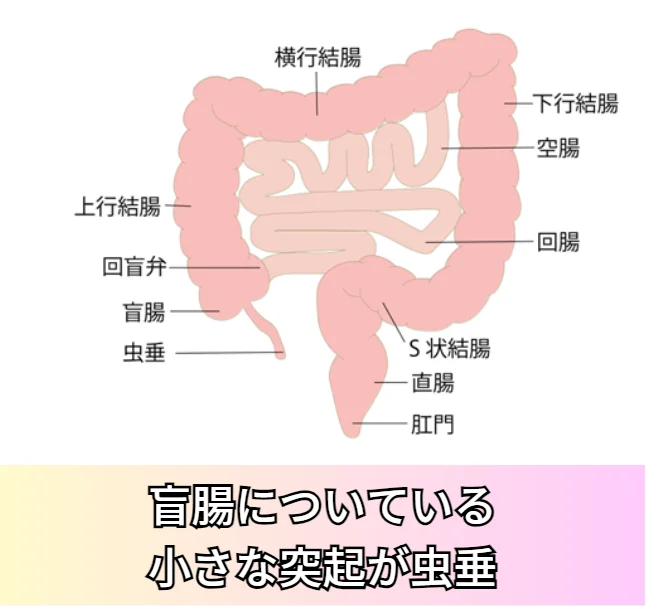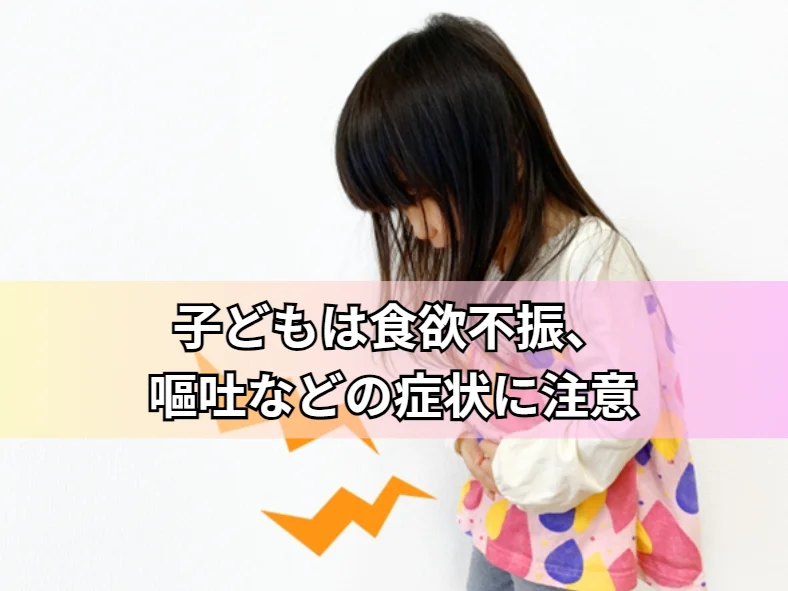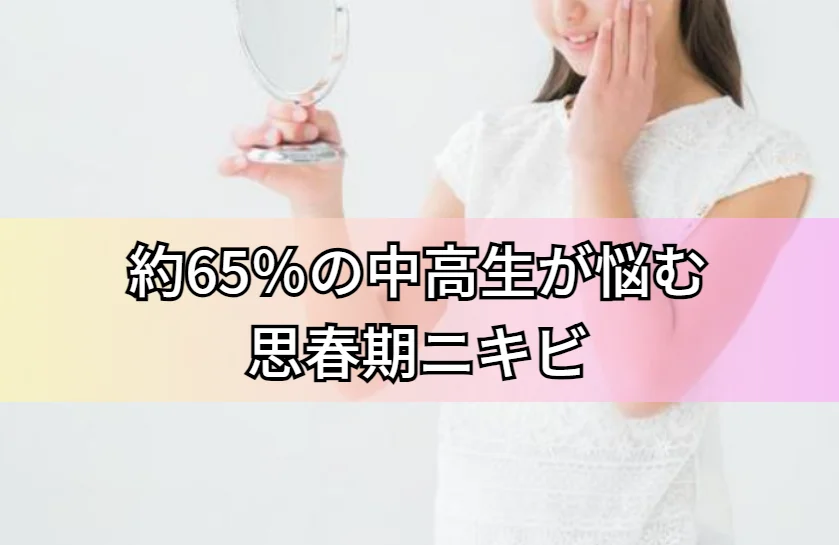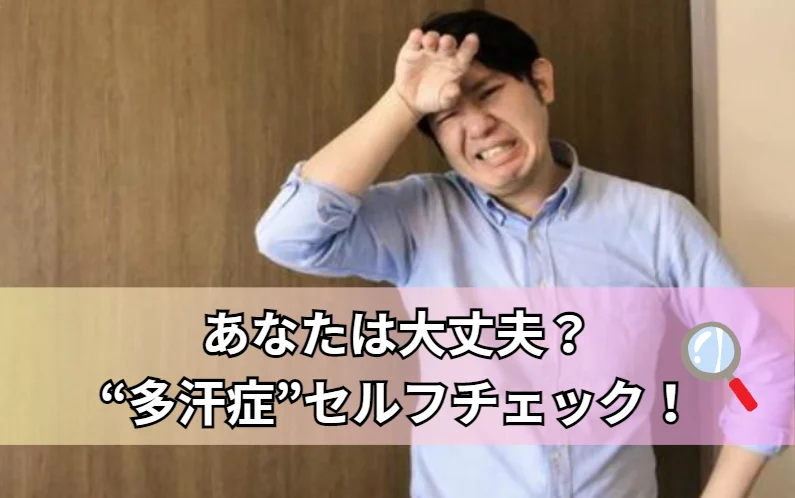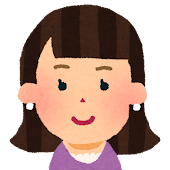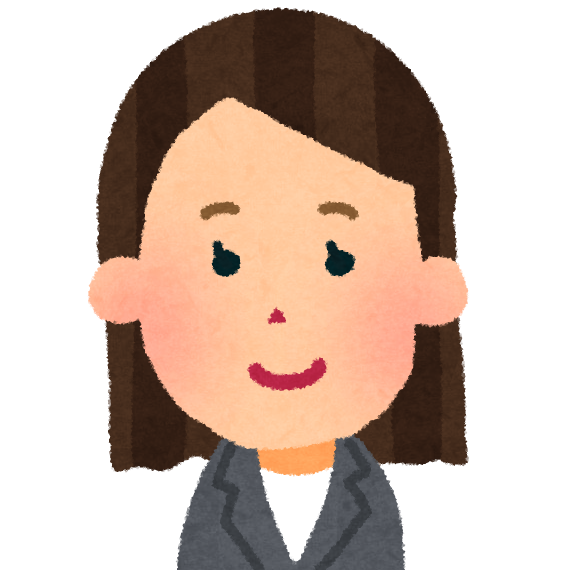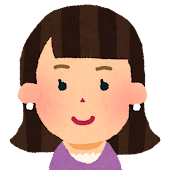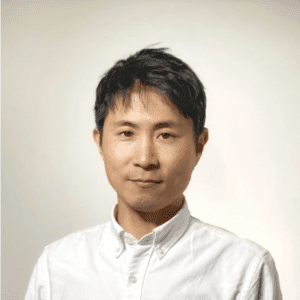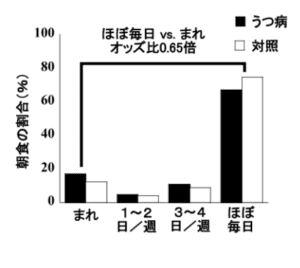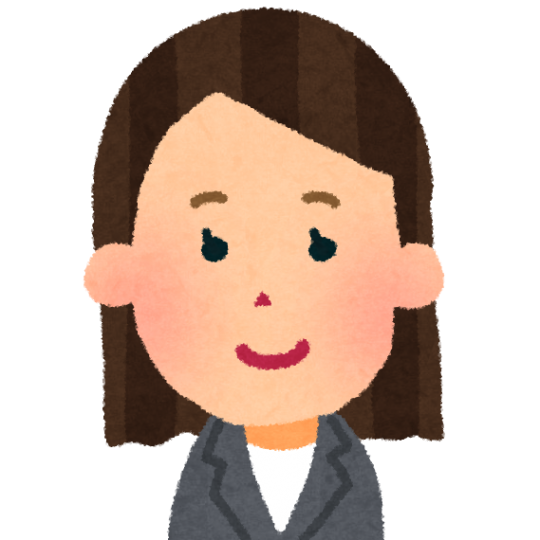第31回【医師監修】安全に美味しい食事を楽しもう!食中毒の原因と予防法
ヨクミルは、ご自宅などのお好きな場所から、PCやスマホで日本人医師にオンライン医療相談ができるサービスです。この連載では、ヨクミルより毎日の生活に役立つ医療や健康情報をお届けします。
【医師監修】安全に美味しい食事を楽しもう!食中毒の原因と予防法

日本では蒸し暑い季節になってきて、メディアなどでは「食中毒」の注意喚起が呼び掛けられています。海外にお住まいの皆さんや海外旅行される方も、日本とは違う食材や環境などで心配なことも多いと思います。そこで今回は、食中毒の原因と家庭でできる予防法などを探ってみました。
細菌、ウイルス、寄生虫など原因は様々
食中毒というと、レストランや旅館などの飲食店での食事が原因と思われがちですが、家庭の食事でも発生する危険性はたくさん潜んでいます。家庭での発生は症状が軽かったり、発症する人数が少なかったりするため、食中毒とは気づかれずに重症化して、死に至ることもありますので、注意をしてください。
食中毒の原因は、細菌、ウイルス、自然毒、化学物質、寄生虫など様々あり、食べてから症状が出るまでの期間やその症状、また予防方法も異なります。細菌は温度や湿度などの条件が揃うと食べ物の中で増殖し、それを食べることにより食中毒を引き起こします。日本では主に夏場に多く発生します。
一方、ウイルスは、冬場に多く発生します。細菌のように食べ物の中では増殖しませんが、低温や乾燥した環境中で長く生存し、食べ物を通じて体内に入ると、腸管内で増殖し食中毒を引き起こします。
発症数や多い原因には、下記のようなものがあります。
- ノロウイルス 牡蠣などの二枚貝に潜む。感染者から食材を介して感染する。
- カンピロバクター 鶏肉や鶏卵に多い。少ない菌で発症する。乾燥と熱に弱い。
- ウエルシュ菌 作り置きされたカレーなどに発生する。加熱で死滅しない。
- サルモネラ菌 鶏卵、食肉、乳製品などに潜む。乾燥に強く熱に弱い。
- アニキサス サバ、アジ、サンマなどの魚介類に寄生する寄生虫。
家庭での食中毒を防ぐ原則とポイント
食中毒を起こす細菌やウイルスが食品についているかどうかは、見ただけや味、においではわかりません。そのため、食中毒を防ぐためには、細菌を食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」という3つが原則となります。
ウイルスは、食品中では増えないので、「増やさない」は、当てはまりません。ウイルスを食品に「つけない」を確実に実行するために、調理者はもちろんのこと、調理器具、調理環境などの調理場全体がウイルスに汚染されていないことが重要です。そのためには、ウイルスを調理場内に「持ち込まない」、食べ物や調理器具にウイルスを「ひろげない」、食べ物にウイルスを「つけない」、付着してしまったウイルスを加熱して「やっつける」の4つが原則となります。
食中毒を予防する食事作りの6つのポイントを紹介しますので、調理時にチェックしてください。

- 表示のある食品は、消費期限等を確認し、新鮮なものを購入しましょう。
- 肉汁や魚等の水分が漏れないように、ビニール袋等にそれぞれ分けて包み、できれば保冷剤等と一緒に持ち帰りましょう。
- 冷蔵や冷凍等の温度管理の必要な食品の購入は、買い物の最後にし、購入したら早めに帰るようにしましょう。

- 持ち帰ったら、必要な食品はすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
- 冷蔵庫や冷凍庫の詰めすぎに注意しましょう。めやすは7割程度です。
- 冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に維持することがめやすです。
- 肉や魚等はビニール袋や容器に入れ、他の食品に肉汁等がかからないようにしましょう。

- ゴミはこまめに捨てましょう。
- タオルやふきんは清潔なものと交換しましょう。
- 井戸水を使用している家庭では、水質に十分注意してください。
- こまめに手を洗いましょう。
- 生の肉や魚等の汁が、果物やサラダ等生で食べる物や調理済みの食品にかからないようにしましょう。
- 生の肉や魚を切った包丁やまな板は、洗ってから熱湯をかけたのち使うことが大切です。
- 冷凍食品等の解凍は冷蔵庫の中や電子レンジで行うとよいでしょう。

- 手を洗いましょう。
- 加熱して調理する食品は十分に加熱しましょう。中心部の温度が75℃で1分間以上加熱することがめやすです。調理を途中でやめる時は、冷蔵庫に入れましょう。再び調理をするときは、十分に加熱しましょう。
- 電子レンジを使う場合は、電子レンジ用の容器、ふたを使い、調理時間に気を付け、熱の伝わりにくい物は、時々かき混ぜることも必要です。

- 食事の前には手を洗いましょう。
- 清潔な手で、清潔な器具を使い、清潔な食器に盛りつけましょう。
- 調理前の食品や調理後の食品は、室温に長く放置してはいけません。

- 手を洗い、残った食品はきれいな器具、皿を使って保存しましょう。
- 早く冷えるように、浅い容器に小分けして保存しましょう。
- 時間が経ち過ぎたら、思い切って捨てましょう。
- 温め直す時も十分に加熱しましょう。めやすは75℃以上です。
- ちょっとでも怪しいと思ったら、口に入れるのはやめましょう。
参考:厚生労働省ホームページ
また、海外では生水や飲食店で提供される料理などで、腹痛を起こすことがあります。衛生的な店を選び、安全性が不明な水や生野菜、カットフルーツ、氷などは口にしないようにしましょう。
食中毒は、上記のようなポイントをきちんと守れば予防できます。それでも、もしお腹が痛くなったり、下痢をしたり、気持ちが悪くなるなど、気になる症状があるときは、早めにヨクミルで日本人医師に相談しましょう。医療機関を受診するべきかどうか迷った時にも相談してください。

監修医紹介
山内美樹先生(内科・総合診療科)
離島に勤務していたこともあり、子どもから大人まで、幅広い年齢の方を診療していました。特に慢性腎臓病、透析患者さんを担当することが多く「腎臓が悪い方の総合内科」を得意分野としています。私の経験が、皆様の悩み軽減のお役に立てればと思います。アメリカ在住。
ヨクミルご利用者の声
ヨクミルでオンライン医療相談をご利用いただいた方からの声をご紹介します。ヨクミルなら自宅などから日本人医師に相談することで、不安を解消できます。

不安なときに専門家の意見が聞ける便利なサービス
アメリカ在住/40代女性 Sさん
原因不明のできものができて不安だったので、皮膚科の先生に相談しました。とても親身になって相談に乗ってくださり、考えられる原因と今後の対処法などを教えていただきました。帰国が近い話をしたら、症状が良くならないようなら日本で病院へ行くように、その前に赤みや膿が出た場合は、現地の皮膚科を受信するようにアドバイスをいただきました。ヨクミルは、病院へ行く時間がない時や専門医の意見が聞きたい時に、とても便利なサービスだと思います。今まで経験したことのない症状が出て、不安になっていたので日本語で相談できてホッとしました。
今ならクーポンプレゼント
「ヨクミルオンライン医療相談サービス」は自宅などの都合の良い場所で、いつでも日本語で専門医に相談ができます。登録料は無料。いざという時慌てないように、登録しておくと安心です。
※ドルのお支払いはその日のレートによって変わります。





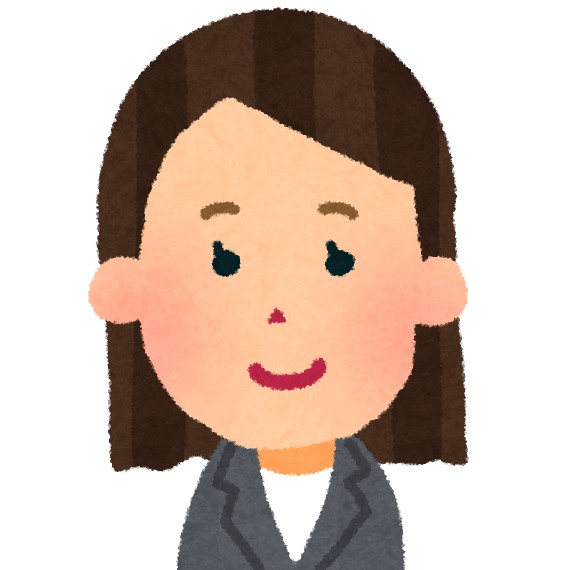





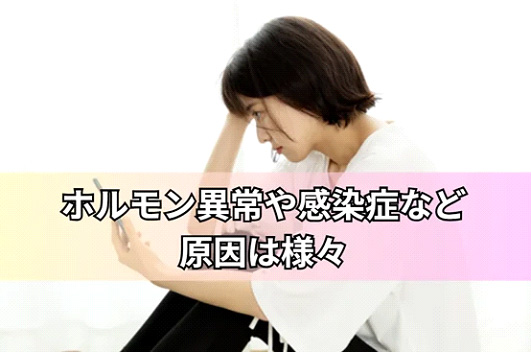

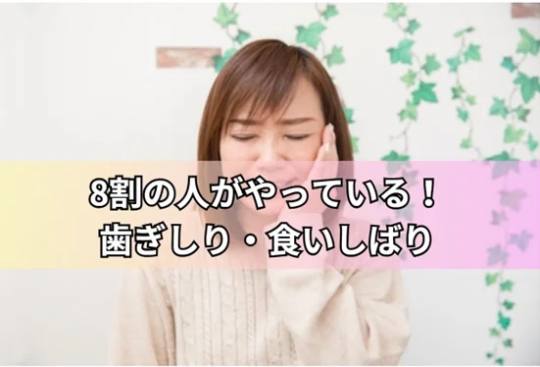


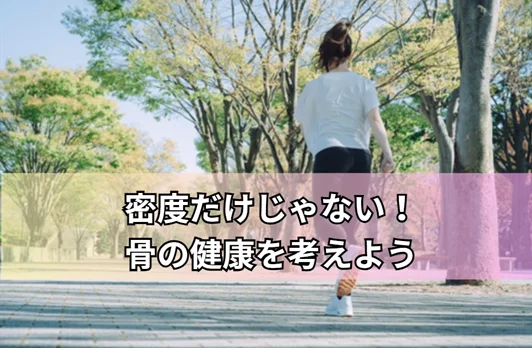
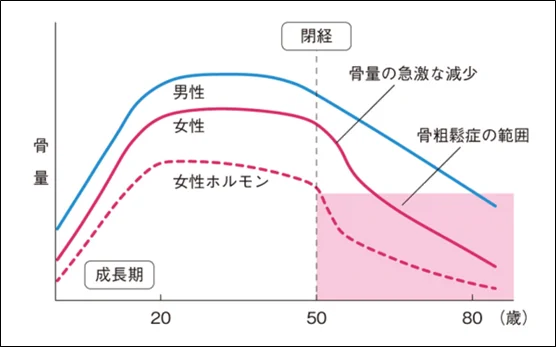
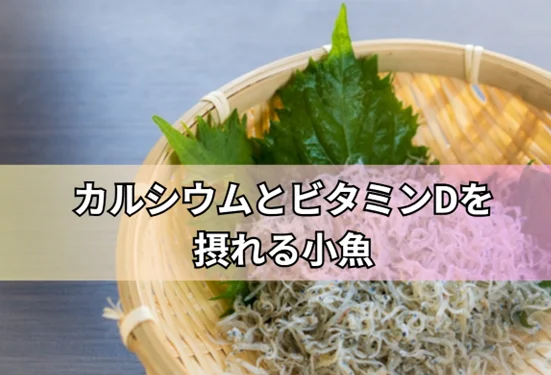
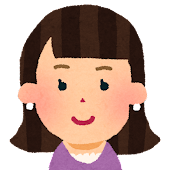

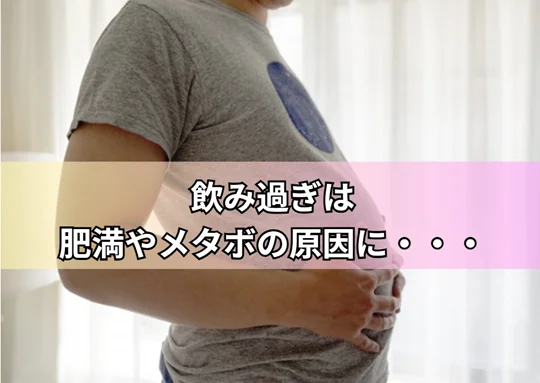


 朝食に野菜やワカメを入れた味噌汁と納豆や、バナナなどのフルーツを入れたヨーグルトを食べると、簡単に両方摂取できます。
朝食に野菜やワカメを入れた味噌汁と納豆や、バナナなどのフルーツを入れたヨーグルトを食べると、簡単に両方摂取できます。